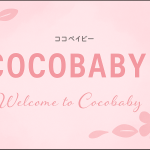序論:なぜ今、不妊治療で漢方が注目されるのか
現代社会では、不妊は多くのカップルが直面する深刻な課題となっています。厚生労働省の統計によると、女性の平均初婚年齢は年々上昇しており、2016年には29.4歳に達しました1。それに伴い、第一子出産時の母親の平均年齢も30.7歳となり2、35歳以上での出産が全体の約3割を占める状況です3 4。
加齢は妊娠能力の低下と密接に関連しており、不妊に悩むカップルの増加は、もはや個人の問題にとどまらず、社会全体で向き合うべきテーマといえます。
体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)といった高度生殖医療(ART)は目覚ましい進歩を遂げ、2021年には国内で過去最多となる69,797人の子どもがARTによって誕生しました5。
しかし、ARTを行っても妊娠に至らないケースや、西洋医学的な検査では原因が特定できない「原因不明不妊」に悩む人も少なくありません。近年では、西洋医学の現場でも東洋医学への関心が高まり、診療に漢方を取り入れるクリニックが増加しています。
こうした中で、西洋医学的治療を補完し、あるいは新たな選択肢として注目されているのが「漢方治療」です。
漢方は、特定の症状だけでなく身体全体のバランスを整え、人間が本来持つ「妊娠する力」を高めることを目的としています。西洋医学が「見える化」や「即効性」を強みとする一方、漢方は「気・血・水」の巡りを整え、時間をかけて妊娠しやすい身体の土台をつくることを得意とします。
この二つのアプローチを組み合わせた「統合医療(ベストミックス)」は、不妊治療の成功率を高める新たな可能性として期待が高まっています。
本記事では、漢方がどのように妊娠に寄与するのか、その科学的な作用機序と臨床的な適応を、国内外の研究や臨床報告をもとに多角的に解説します。漢方治療の「可能性」と「限界」を正しく理解し、より賢明な治療選択の一助とすることを目指します。
漢方治療はなぜ効くのか:科学的視点から探る作用機序
漢方薬が不妊治療において効果を発揮する背景には、「多成分・多標的(multi-component, multi-target)」という特性があります。
単一の有効成分で特定の標的に作用する西洋薬とは異なり、漢方薬は複数の生薬を組み合わせることで、神経系・内分泌系・免疫系など、身体全体のネットワークに穏やかに働きかけます。これにより自己治癒力を引き出し、妊娠しやすい状態へ導くことを目指します。
女性不妊に対する主な作用
ホルモンバランスの調整
月経周期は、視床下部・下垂体・卵巣が連携して分泌するホルモンによって精密にコントロールされています。漢方薬はこのホルモン分泌の司令塔に作用し、乱れたリズムを整えると考えられています。
たとえば「温経湯」が多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)患者のLH高値を正常化させたという報告や、「当帰芍薬散」によるホルモン分泌調整の可能性を示す基礎研究もあります。ただし、ヒトでの高品質なエビデンスは今後の課題です。
卵巣・子宮環境の改善
良質な卵子を育て、受精卵が着床するためには、卵巣や子宮への血流が重要です。
漢方では「瘀血(おけつ)」、つまり血の巡りの滞りが不妊の大きな要因と考えられています。
「桂枝茯苓丸」などの駆瘀血薬は骨盤内の血流を促し、卵巣への栄養供給を改善、子宮内膜を整えることで妊娠しやすい環境を整えるとされています。
酸化ストレスの軽減と免疫の調整
活性酸素による酸化ストレスは卵子の質を低下させます。漢方薬に含まれる抗酸化成分は卵子を保護し、また着床時に母体が受精卵を攻撃しないよう免疫を穏やかに調整する「安胎作用」も報告されています。
男性不妊に対する作用
不妊原因の約半数は男性側にもあり、主に精子の数や運動性の低下が関係します。
精子形成には約74日を要し6 7、酸化ストレスに非常に弱いことが知られています。実際、男性不妊の30〜80%には酸化ストレスの関与があるとされます8 9。
漢方薬の抗酸化作用は精子を保護し、精液所見の改善を助ける可能性があります。臨床的には、漢方薬とビタミンEなどの抗酸化物質を併用した際に改善が見られるケースも報告されています。
どのようなケースに有効か
西洋医学の診断名に基づくケース
排卵障害(PCOSなど)
2016年のコクラン・レビューでは、漢方薬とクロミフェン併用群が、クロミフェン単独群より有意に高い妊娠率(オッズ比2.62)を示しました10。
高年齢・卵巣機能低下
加齢による卵巣機能低下に対し、漢方薬を併用したIVFで、卵子・受精卵数の改善や出産例が報告されています11。
原因不明不妊
西洋医学で原因が不明な場合でも、漢方では「冷え」「ストレス」「血行不良」などの体質異常が見つかることがあります。これらを整えることで妊娠に至るケースもあります。
「証」に基づくケース(体質別アプローチ)
漢方では、個々の体質(証)に合わせて処方を決める「随証治療」を行います。
不妊でよく見られる証には、「気滞瘀血」「腎虚」「血虚」「水滞」などがあります。
ある研究では、卵巣機能不全不妊症100例の分析で、「瘀血(71%)」「水毒(67%)」「少陽病(69%)」が多く見られたと報告されています12。
このように、専門家による正確な証の見極めが治療効果の鍵を握ります。
安全性と限界
漢方薬は自然由来ですが、薬である以上、副作用の可能性があります。
胃腸障害や皮膚症状のほか、甘草の長期服用による偽アルドステロン症(むくみ・高血圧)13、まれに間質性肺炎14や肝機能障害15も報告されています。必ず専門家の指導のもとで使用することが重要です。 また、卵管閉塞や無精子症などの器質的疾患には、西洋医学的治療(手術・体外受精など)が第一選択となります。漢方は即効性が低く、効果が現れるまでに数か月を要します。さらに、科学的エビデンスの蓄積は発展途上であることも理解しておく必要があります10。
不妊治療における漢方の賢い活用法
現代の不妊治療では、西洋医学と漢方の長所を組み合わせる「統合医療(ベストミックス)」が理想的なアプローチです。
正確な診断を軸に、漢方で体調を整えながら治療を進める。この二人三脚の方法は、治療効果を高めるだけでなく、心身の負担を軽減し、妊娠・出産への道を最短化する可能性があります。
漢方治療を検討する際は、まず信頼できる産婦人科で現状を把握し、不妊治療と漢方の両方に精通した専門家に相談してください。
自身の体質(証)に合った処方を受けることが、安全で効果的な妊活を進めるうえでの最も賢明な一歩となるでしょう。
脚注
- 厚生労働省. (2017). 平成28年(2016)人口動態統計月報年計(概数)の概況 ↩︎
- 厚生労働省. (2022). 令和3年度「出生に関する統計」の概況 ↩︎
- ヒロクリニック. (2025). 高齢出産は35歳から?障害やダウン症リスクについて【医師監修】 ↩︎
- CEMクリニック. (n.d.). 高齢出産の年齢は何歳から?リスクと対策について解説! ↩︎
- 日本産科婦人科学会. (2023). 2021年 ARTデータブック ↩︎
- Griswold, M. D. (2016). Spermatogenesis: The Commitment to Meiosis. Physiological Reviews, 96(1), 1–17 ↩︎
- Wikipedia. (2024). Spermatogenesis ↩︎
- Barati, E., Nikzad, H., & Karimian, M. (2020). Oxidative stress and male infertility: current knowledge of pathophysiology and role of antioxidant therapy in disease management. Cellular and Molecular Life Sciences, 77(1), 93–113 ↩︎
- Wagner, H., Cheng, J. W., & Ko, E. Y. (2018). Role of reactive oxygen species in male infertility. Urology, 111, 1–7 ↩︎
- Zhou, K., Zhang, J., Xu, L., Wu, T., & Lim, C.E. D. (2016). Chinese herbal medicine for subfertile women with polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10) ↩︎
- 高橋浩子, 日笠久美, 鎌田周作, & 鎌田ゆかり. (2018). 体外受精の段階に合わせ決まったパターンで漢方薬を投与した20症例. 日本東洋医学雑誌, 69(3), 252–261 ↩︎
- 假野隆司, 土方康世, 清水正彦, 河田佳代子, 日笠久美, & 後山尚久. (2008). 随証漢方療法で生児を獲得した卵巣機能不全不妊症100例の漢方医学的ならびに西洋医学的解析. 日本東洋医学雑誌, 59(1), 35–45 ↩︎
- 厚生労働省. (n.d.). 重篤副作用疾患別対応マニュアル:偽アルドステロン症 ↩︎
- 中医薬研究室. (2004). 観察与思考:“小柴胡事件”帯給我們的警示 ↩︎
- 萬谷直樹, 嶋田豊, & 柴原直樹. (2017). 当院における黄芩含有漢方薬による肝障害の頻度について. 日本東洋医学雑誌, 68(4), 377–383 ↩︎
- Zhou, K., Zhang, J., Xu, L., Wu, T., & Lim, C.E. D. (2016). Chinese herbal medicine for subfertile women with polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10) ↩︎
専門家コメント
住吉忍先生より
本記事では、漢方の多面的な力を科学的・臨床的両面から非常に丁寧にまとめてくださり、大変意義のある内容だと感じました。 不妊治療は「原因を治す医療」だけではなく、「妊娠できる身体を育てる医療」でもあります。
漢方はまさにその“土台づくり”を担う存在です。 現場で多くの患者さまと向き合う中で実感するのは、漢方を併用することで「体温や月経リズムの改善」「睡眠や気分の安定」「採卵数や内膜の質の変化」など、数値化できる変化と同時に、心身の調和が生まれていくことです。
こうした「全体性へのアプローチ」が、西洋医学的治療の成功率を高め、結果として妊娠・出産に繋がるケースを数多く見てきました。 一方で、記事にもある通り、漢方は即効性を求めるものではなく、個々の体質や生活習慣に合わせた継続的な取り組みが不可欠です。
科学的エビデンスの蓄積とともに、「どのような方に、どのような段階で漢方を取り入れるのが最も有効か」を、今後も臨床データと経験をもとに発信してまいります。
西洋医学と東洋医学の“補完しあえる医療”が、より多くの方にとって希望ある選択肢となるよう、引き続き現場から貢献していきたいと思います。
住吉忍先生プロフィール
薬剤師・国際中医師
株式会社ウィメンズ漢方代表、臨床漢方カウンセリング協会代表理事。薬剤師・国際中医師として、全国23か所の婦人科・不妊治療専門クリニックで漢方外来を担当。不妊治療、特に難治性症例やプレコンセプションケア、更年期に対応した漢方処方を得意とし、西洋医学と東洋医学を融合させた治療サポートを行っています。体質やライフステージに合わせたオーダーメイドのカウンセリングを通じて、女性の一生を支える医療の実現を目指しています。
【関連リンク】
ウイメンズ漢方
https://womens-kampo.co.jp/