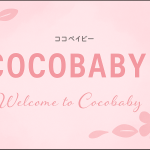なぜ今、妊活で「食」が注目されるのか?
世界的に不妊に悩むカップルは増加しており、世界保健機関(WHO)の2023年の報告によれば、成人の約6人に1人が生涯で不妊を経験するとされています。この背景には、晩婚化や社会環境の変化など様々な要因が絡み合っています。その中で個々人が主体的に取り組める改善策として、ライフスタイルの見直し、特に「食事」が妊娠の可能性を高めるための重要な鍵として科学的に注目を集めています。
本記事では、過去5年間の信頼性の高い学術論文や臨床試験の結果に基づき、食事と妊娠の関係を科学的根拠(エビデンス)を基に解き明かします。かつて不妊は主に女性側の問題と捉えられがちでしたが、近年の研究では、不妊原因の約半数に男性因子が関与していることが明らかになっています。食事は男女双方にとって改善可能なアプローチになるというわけです。
妊娠しやすい身体をつくる食事法:最新エビデンスの全体像
妊娠しやすい身体をつくる食事法として、特定の栄養素を単体で摂取するよりも、日々の食事全体のパターン、つまり「何をどのように組み合わせて食べるか」がより重要であるという考え方が主流になりつつあります。
地中海式食事法のススメ
最も多くの科学的エビデンスが蓄積されているのが「地中海式食事法」です。この食事法は、オリーブオイル(一価不飽和脂肪酸)、魚(オメガ3脂肪酸)、野菜、果物、全粒穀物、豆類を豊富に摂取し、赤身肉や加工肉の摂取を控えるのが特徴です。
複数の研究がその有効性を示しており、例えば、地中海式食事法の遵守度が高い女性は、体外受精(IVF)における臨床的妊娠率が向上する傾向が見られました。あるメタアナリシスでは、地中海式食事スコアが高いと臨床的妊娠の確率が1.4倍になるという結果も報告されています。また、別の研究では、この食事法が胚盤胞(着床直前の段階の胚)の形成を改善する可能性についても示されています。

抗炎症食の重要性
体内で持続する軽微な「慢性炎症」は、生殖機能に多岐にわたる悪影響を及ぼすことが知られています。炎症は、排卵サイクルの乱れ、卵子の質の低下、さらには受精卵の着床不全の原因となり得ます。
地中海式食事法は、まさに代表的な抗炎症食です。その構成要素である一価不飽和脂肪酸、n-3系多価不飽和脂肪酸、フラボノイドなどが、体内の炎症を抑える働きをします。逆に、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、精製された糖質を多く含む高脂肪・高カロリーな「欧米型」の食事は、体内の炎症マーカー(CRPやIL-6など)を上昇させ、不妊のリスクを高める可能性があると指摘されています。
血糖コントロールを意識した食事(低GI/GL食)
食事による血糖値の急激な上昇は、インスリンの過剰分泌を招き、「インスリン抵抗性」という状態を引き起こすことがあります。これは、細胞がインスリンに反応しにくくなる状態で、特に排卵障害の主要な原因である多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と深く関連しています。
研究によると、高GI・高GLの食事を続けている女性は、不妊のリスクが高まることが示唆されています。具体的には、白米、白いパン、砂糖などの精製された炭水化物を控え、食物繊維が豊富な全粒穀物(玄米、全粒粉パンなど)、野菜、豆類を選ぶことが推奨されます。
キーポイント:食事パターンの要点
マクロな視点が重要:個々の栄養素だけでなく、食事全体のバランスが妊娠しやすい身体の土台を作る。
地中海式食事法が第一選択:豊富なエビデンスに裏付けられており、抗炎症作用と栄養バランスに優れる。
炎症と血糖を制する:抗炎症作用のある食品を選び、血糖値を急上昇させない低GI/GL食を心掛けることが、ホルモンバランスを整える鍵となる。
注目すべき栄養素と食品:何を「選び」、何を「避ける」べきか
タンパク質:植物性タンパク質の優位性
ハーバード大学公衆衛生大学院が実施した大規模な追跡調査「Nurses’ Health Study II」のデータを分析した研究では、動物性タンパク質(特に赤身肉や加工肉)の摂取が多いほど排卵障害による不妊のリスクが高まり、逆に植物性タンパク質(豆類など)の摂取を増やすとリスクが低下するという関連が見出されました。日々の食事で肉中心のメニューが多い方は、豆腐、納豆、レンズ豆、ひよこ豆などを意識的に取り入れることが推奨されます。
脂質:「良質な油」の選択
マーガリンやショートニング、加工食品に多く含まれるトランス脂肪酸は、炎症を促進し、インスリン抵抗性を悪化させることで、排卵や着床に悪影響を及ぼすことが知られています。
一方で、積極的に摂取したいのが「良質な油」です。オリーブオイルやアボカドに豊富な一価不飽和脂肪酸(MUFA)や、青魚(サバ、イワシなど)や亜麻仁油、えごま油に含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸(PUFA)は、抗炎症作用を持ち、生殖機能に好影響をもたらす可能性があります。
カフェイン:摂取量とリスクのバランス
コーヒーや紅茶に含まれるカフェインが妊活に与える影響は、多くの人が気になるところでしょう。結論から言うと、カフェイン摂取が直接的に妊娠しにくさにつながるという明確な証拠は、現在のところ
限定的です。複数の研究を統合したメタアナリシスでも、体外受精の妊娠率や出産率とカフェイン摂取量との間に有意な関連は見出されていません。
しかし、妊娠後の影響については注意が必要です。。2017年に行われたシステマティックレビューおよびメタアナリシスでは、妊娠初期のカフェイン摂取量と自然流産(SAB)のリスクとの間には、用量依存的な関係があることが示されました。具体的には、1日300mgのカフェイン摂取で流産リスクが1.37倍に、600mgでは2.32倍に上昇すると報告されています。

男性の妊活と食事:精子の質をめぐる最新の議論
不妊原因の約半分は男性側にあるとされています。その中でも精子の質(運動率、形態、DNAの損傷度など)は重要な要素です。
酸化ストレスと精子へのダメージ
男性不妊のメカニズムの一つとして「酸化ストレス」が注目されています。体内で過剰に発生した活性酸素種(ROS)は、細胞を傷つける「サビ」のようなものです。精子は特にこの酸化ストレスに弱く、ROSによって細胞膜が損傷すると運動能力が低下し、さらに核内のDNAが断片化(精子DNA断片化)すると、受精能力の低下や、受精後の胚発生の停止、流産の原因になると考えられています。
抗酸化サプリメントは本当に有効か?
男性不妊における酸化ストレス対策として、「抗酸化サプリメントの有効説」が長年支持されてきました。しかし、この「抗酸化サプリメント有効説」に疑問を投げかける、質の高い研究結果が近年相次いで報告されています。最も衝撃的だったのは、2025年に医学雑誌『JAMA Network Open』で発表された、オランダで行われた大規模なランダム化比較試験(SUMMER trial)の結果です。
この試験では、1,171人の不妊治療中の男性を2群に分け、一方は複数の抗酸化物質を含むサプリメント(Impryl)を、もう一方は偽薬(プラセボ)を6ヶ月間摂取しました。その結果、抗酸化サプリメント群の妊娠率はプラセボ群と比較して改善しなかったのです。
これら最新の研究結果は、安易に市販の抗酸化サプリメントに頼ることへの警鐘を鳴らしています。現時点での最も賢明なアプローチは、特定のサプリメントに依存するのではなく、野菜、果物、ナッツ、魚など多様な食品から様々な種類の抗酸化物質をバランス良く摂取する「食事」を基本とすることです。サプリメントの使用を検討する場合は、自己判断せず、必ず医師に相談することが大切です。
また、サプリメントも、メーカーによって質が大きく変わることは明らかになっています。信頼のおける医師や管理栄養士の推薦があるサプリメントを選択しましょう。

PCOSと食事療法の最前線
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、月経不順や排卵障害を引き起こす女性の最も一般的な内分泌疾患であり、不妊の主要な原因の一つです。
PCOSの核心:インスリン抵抗性との関連
PCOSの病態の核心には「インスリン抵抗性」があります。これは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きが悪くなる状態で、PCOS女性の多くに見られます。この高アンドロゲン血症が、卵胞の正常な発育を妨げ、排卵障害を引き起こすのです。
有効性が示唆される食事アプローチ
肥満を伴うPCOSの場合、体重を5〜10%減らすだけでも、インスリン感受性が劇的に改善し、自然に月経周期が回復することがあります。
あるメタアナリシスでは、BMIが25以上のPCOS女性において、カロリー制限食や低カロリー・低糖質を組み合わせた食事が、代謝指標やホルモンバランス、妊娠関連の成果を改善したと報告されています。
糖質を極端に制限し、脂質を主なエネルギー源とするケトジェニックダイエットも、PCOSに対する有効性が注目されています。ある研究では、PCOS女性がケトジェニックダイエットを実践したところ 、インスリンレベルや男性ホルモンが改善し、高い妊娠率が報告されました。
食事療法と薬物療法(メトホルミン)の相乗効果
研究によると、メトホルミン(インスリンの働きを助け、血糖値を改善する薬)は、食事療法や運動療法と組み合わせることで、月経周期の回復や排卵誘発の効果がさらに高まることが示されています。さらに、メトホルミンと糖質制限食の組み合わせが、子宮内膜の着床環境に関わる遺伝子の発現を改善する可能性も報告されています。
腸内フローラと生殖医療
近年、医学のあらゆる分野で「マイクロバイオーム(微生物叢)」、特に腸内に生息する細菌群である「腸内フローラ」の重要性が認識されていますが、生殖医療も例外ではありません。
腸内細菌は、私たちが食べたものを分解する過程で、短鎖脂肪酸、ビタミン、神経伝達物質など、様々な代謝産物を産生します。これらの物質は血流に乗って全身を巡り、免疫系の調節、ホルモンバランスの維持、さらには卵巣や子宮内膜の環境にも影響を与えることが分かってきました。
実際に、PCOSや子宮内膜症といった生殖障害を持つ女性は、健常な女性と比べて腸内フローラの構成が異なっているという報告が複数あります。
まとめ:明日から始めよう、妊活のための食生活改善プラン
特定の栄養素やサプリメントに頼るのではなく、日々の食事全体を整えることこそ、妊娠しやすい身体づくりの第一歩です。
変化はすぐには見えないかもしれませんが、その一歩を踏み出すこと自体が未来への投資です。
今日から、自分の身体と向き合う時間を少しずつ増やしていきましょう。
実践的アドバイス:妊活のための食生活チェックリスト
✅ 男女共通
目指すは「地中海式食事」:食事の中心に、色とりどりの野菜、果物、全粒穀物、豆類を取り入れましょう。調理油はオリーブオイルを基本に。
加工食品と精製糖は減らす:スナック菓子、甘い飲み物、インスタント食品は、体内の炎症を促進し、血糖値を乱す元凶です。できるだけ避けましょう。
適正体重を維持する:肥満もやせすぎもホルモンバランスを崩す原因になります。BMI(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)が18.5〜24.9の範囲を目標にしましょう。
✅ 女性向け
タンパク質は「植物性」を意識:肉を食べる日、魚を食べる日、そして豆腐や豆料理を主役にする日を設け、バランスを取りましょう。
カフェインは控えめに:コーヒーや緑茶が好きでも、1日2杯程度までを目安に。デカフェ(カフェインを取り除いたコーヒーやお茶などの飲み物)の選択肢も視野に入れましょう。
✅ 男性向け
抗酸化サプリに頼らない:最新の研究は、安易なサプリメント摂取に警鐘を鳴らしています。抗酸化物質は、様々な色の野菜や果物から摂るのが最も安全で効果的です。
亜鉛やセレンを食品から :精子の形成に必要な亜鉛(牡蠣、赤身肉、ナッツ)やセレン(魚介類、卵)を食事から意識して摂取しましょう。
参考文献
- The Role of the Mediterranean Diet in Assisted Reproduction – MDPI
- The association between caffeine and alcohol consumption and IVF – Acta Obstetricia et GynecologicaScandinavica
- Association between coffee or caffeine consumption and fecundity – PMC
- The Effect of Metformin and Carbohydrate-Controlled Diet on DNA – PMC
- Advances in the study of the correlation between insulin resistance – PMC
- The impact of dietary interventions on polycystic ovary syndrome – PMC
- Ketogenic diet improves fertility in patients with polycystic ovary – Frontiers in Nutrition
- Mediterranean diet improves blastocyst formation in women – Frontiers in Nutrition
- Glycemic index, glycemic load, dietary inflammatory index, and risk – PMC
- Antioxidant pretreatment for male partner before ART for male factor – PMC
- Metformin for Polycystic Ovary Syndrome – AAFP
- Clinical trial disproves claims that antioxidant supplement boosts – News Medical
- Female infertility and diet, is there a role for a personalized – PMC
- Female Fertility and the Nutritional Approach: The Most Essential – PMC
- A comprehensive review of polycystic ovary syndrome (PCOS) and – ScienceDirect
- From gut to gamete: how the microbiome influences fertility and – PMC
- Anti-Inflammatory Diets in Fertility: An Evidence Review – PubMed
- The impact of gut microbiota on reproductive functions – Frontiers in Immunology
- Dietary Inflammatory Index and female infertility – Frontiers in Nutrition