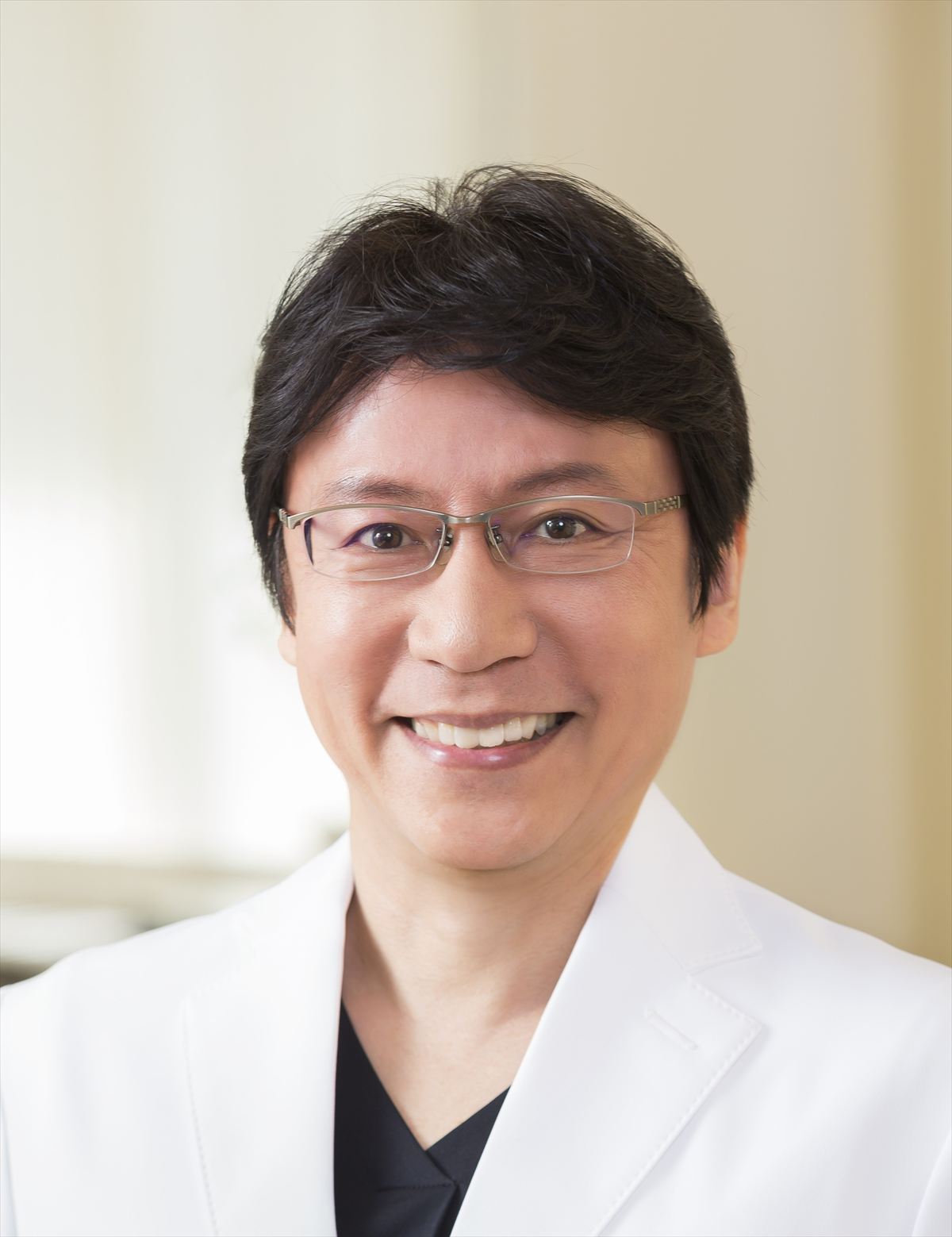はじめに
近年、健康意識の高まりとともに「 プレコンセプションケア」という言葉を耳にする機会が増えました。これは、将来の妊娠や出産に備えるだけでなく、自分自身の健康な未来を築くための新しいヘルスケアの考え方です。この記事では、プレコンセプションケアの中核をなす「健診(プレコンチェック)」に焦点を当て、その内容から活用法、公的支援までを網羅的に解説します。健診を最大限に活用し、自分と未来の家族の健康を守るための一歩を踏み出しましょう。

1. プレコンセプションケア(プレコン)とは?―単なる「妊活」ではない、新しい健康常識
プレコンセプションケア、通称「プレコン」は、単に妊娠を目指す活動(妊活)とは一線を画す、より広範な健康管理の概念です。
1.1. プレコンの定義:未来を見据えた包括的ヘルスケア
プレコンセプションケアは、英語の「Pre-conception(妊娠前)」と「Care(ケア)」を組み合わせた言葉です。 国立成育医療研究センターによると、これは「将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと」と定義されています。重要なのは、 妊娠を望む人だけでなく、妊娠の可能性のあるすべての若い世代の男女にとって重要な取り組みであるという点です。その目的は、現在の健康を増進し、将来の健全な妊娠・出産につなげ、さらには次世代の子どもたちの健康にも貢献することにあります。
1.2. なぜ今、プレコンが必要なのか?
現代社会では、晩婚化やライフスタイルの多様化が進んでいます。それに伴い、妊娠・出産に関する健康リスクも変化しています。プレコンセプションケアは、これらのリスクを事前に把握し、低減させるために不可欠です。
WHO(世界保健機関)も、妊娠前の健康管理の重要性を提唱しており、「妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と定義しています。これにより、妊娠糖尿病や高血圧などの合併症リスク、不妊のリスクを減らし、母子の健康を守ることが期待されます。
また、胎児の重要な臓器が形成されるのは妊娠初期ですが、多くの女性が妊娠に気づくのはその後です。そのため、妊娠前から健康な身体づくりをしておくことが、赤ちゃんの健やかな発育にとって極めて重要になります。
1.3. 対象は誰?―女性だけでなく、男性とカップルで取り組む意義
プレコンセプションケアは、しばしば女性のためのものと誤解されがちですが、 男性の健康状態も妊娠の成否や子どもの健康に大きく影響します。世界保健機関(WHO)の調査では、不妊の原因の約半数(48%)に男性側も関わっていると報告されています。
そのため、プレコンは女性一人で取り組むのではなく、カップルで、あるいは男性が単独で自身の健康を見直すことも非常に重要です。自治体の助成事業でも、 千葉市のように夫婦での受診を助成の条件とするケースもあり、パートナーと共に健康について考える良い機会となります。
2. プレコンセプションケア健診(プレコンチェック)で何を調べるのか?
プレコンセプションケア健診(プレコンチェック)は、自分たちの健康状態を客観的に把握するための重要なステップです。医療機関によって内容は異なりますが、ここでは一般的な検査項目を紹介します。
2.1. 健診の目的:自分の「現在地」を知る第一歩
プレコンチェックの最大の目的は、 妊娠・出産に影響を与えうる健康上のリスクを早期に発見することです。妊娠は女性の身体にとって「負荷テスト」とも言われるほど大きな負担がかかります。 国立成育医療研究センターでは、健診とカウンセリングを通じて、栄養、生活習慣、持病、感染症など多角的な視点から現在の健康状態を評価し、より良い状態に整えることを目指しています。

2.2. 【男女共通】基本となる健康状態と感染症のチェック
男女ともに受けるべき基本的な検査には、全身の健康状態を把握するものと、母子感染のリスクがある感染症を調べるものが含まれます。
- 一般的な健康診断:血圧測定、血液検査(貧血、血糖値、コレステロール、肝機能、腎機能など)、尿検査(糖、たんぱく)を行い、高血圧や糖尿病、貧血などの基礎疾患がないかを確認します。
-
感染症検査:特に重要なのが、母子感染を引き起こす可能性のある以下の感染症です。
- 風しん抗体検査:妊娠初期に風しんにかかると、赤ちゃんに心疾患や難聴などの障害(先天性風しん症候群)が起こるリスクがあります。抗体がない場合は、妊娠前にワクチン接種が必要です。
- B型・C型肝炎、HIV、梅毒:これらは血液や産道、母乳を介して赤ちゃんに感染する可能性があります。早期発見と適切な管理で母子感染のリスクを大幅に低減できます。
- 性感染症(クラミジア、淋菌など):不妊や流産、早産の原因となることがあるため、事前のチェックと治療が推奨されます。
2.3. 【女性向け】妊娠と出産に関わる専門的な検査項目
女性は、妊娠・出産に直接関わる生殖機能を中心に、より専門的な検査を行います。
- 婦人科診察・経膣超音波検査:子宮筋腫や卵巣嚢腫、子宮内膜症など、妊娠の妨げになる可能性のある病気がないかを調べます。
- AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査:卵巣内にどれくらいの数の卵子が残っているかの目安(卵巣予備能)を評価する血液検査です。
- ホルモン検査(LH, FSH, エストロゲンなど):月経周期に関わるホルモンのバランスを調べ、排卵障害などがないかを確認します。
- 甲状腺機能検査:甲状腺ホルモンの異常は、不妊や流産のリスクを高めることが知られています。
2.4. 【男性向け】見過ごされがちな「男性不妊」のリスクを調べる検査
男性側の検査も、健やかな妊娠のためには不可欠です。近年、男性向けの検査項目も拡充されています。
- 精液検査:精子の数、運動率、形態などを調べ、精子の状態を評価します。これは男性の妊よう性(妊娠させる力)を知るための最も基本的な検査です。
- ホルモン検査(テストステロン, LH, FSHなど):精子を作る機能に影響を与えるホルモンの異常がないかを確認します。
- 超音波検査:精巣やその周辺の血流などを調べ、精索静脈瘤などの異常がないかを確認します。
3. 健診結果をどう活かす?―具体的なアクションプラン
健診は受けて終わりではありません。結果を基に、具体的な行動に移すことが最も重要です。
3.1. 生活習慣の改善:今日から始められる5つのアクション
検査で異常が見つからなかった場合でも、より健康な状態を目指して生活習慣を見直しましょう。以下は、今日からでも始められる具体的なアクションです。
- バランスの取れた食事:1日3食、主食・主菜・副菜をそろえることを意識しましょう。特に緑黄色野菜や果物を積極的に摂ることが推奨されます。
- 適正体重の維持と適度な運動:「やせ」も「肥満」もホルモンバランスの乱れや不妊の原因となります。 船橋市の資料によると、適度な運動は血流を改善し、心身に良い影響を与えます。ウォーキングなど、続けやすい運動から始めましょう。
- 禁煙と節度ある飲酒:喫煙は流産や早産、低出生体重児のリスクを高めます。 厚生労働省は妊娠前の完全な禁煙を推奨しています。アルコールも過度な摂取は避けましょう。
- 十分な睡眠:睡眠不足はホルモンバランスに影響を与えるため、規則正しい生活リズムを心がけ、質の良い睡眠を確保することが大切です。
- ストレスマネジメント:強いストレスは心身の健康に悪影響を及ぼします。趣味の時間を持つ、リラックスできる方法を見つけるなど、自分に合った方法でストレスと上手に付き合いましょう。

3.2. 栄養とサプリメント:特に重要な「葉酸」の役割
プレコンセプションケアにおいて、特に重要視される栄養素が 葉酸です。葉酸は、胎児の神経管閉鎖障害という先天性異常のリスクを低減する効果があることが科学的に証明されています。
厚生労働省や日本産婦人科学会は、妊娠を計画している女性に対し、妊娠1か月以上前から妊娠3か月までの間、通常の食事に加えて 1日400μg(0.4mg)の葉酸をサプリメントで摂取することを推奨しています。
葉酸はほうれん草やブロッコリーなどの食品にも含まれますが、食事だけで推奨量を摂取するのは難しいため、サプリメントの活用が効果的です。ただし、サプリメントはあくまで補助的なものです。現時点で「妊娠率の向上」が科学的に証明されたサプリメントはないため、過剰な期待はせず、医師や管理栄養士に相談の上で適切に利用しましょう。

3.3. 専門家とのカウンセリング:不安を解消し、次のステップへ
健診結果で何らかのリスクや異常が見つかった場合、あるいは結果の解釈に不安がある場合は、専門家によるカウンセリングが非常に有効です。医師や助産師、管理栄養士などが、個々の状況に合わせて専門的なアドバイスを提供してくれます。
例えば、持病がある場合は妊娠に向けた治療計画の見直し、食生活に課題があれば具体的な改善方法の指導など、専門的なサポートを受けることで、安心して次のステップに進むことができます。オンラインでのカウンセリングを提供している医療機関も増えています。
4. 知っておきたい公的支援と企業の取り組み
プレコンセプションケアは個人だけの取り組みではありません。社会全体でサポートする動きが広がっています。
4.1. 自治体の助成制度を活用する(東京都「TOKYOプレコンゼミ」を例に)
一部の自治体では、プレコンセプションケアに関する健診費用を助成する制度を設けています。代表的な例が、 東京都の「TOKYOプレコンゼミ」です。
この制度は、都が開催するオンラインゼミを受講した18歳から39歳の都民を対象に、指定の医療機関で受けた検査費用の一部を助成するものです。助成額は男女それぞれ上限3万円(令和7年度時点)で、前述したような専門的な検査の多くが対象となっています。お住まいの自治体でも同様の制度がないか、ぜひ確認してみてください。
【東京都の助成制度の流れ(令和7年度の例)】
1. オンライン講座「TOKYOプレコンゼミ」を受講する。
2. 登録医療機関で、医師と相談の上、対象となる検査を受ける。
3. 検査後にアンケートに回答し、助成金を申請する。
4.2. 職場でのサポート:「健康経営」としてのプレコンセプションケア
近年、従業員の健康を経営的な視点で捉える「健康経営」の一環として、プレコンセプションケアを支援する企業が増えています。企業がプレコンを支援することは、従業員がライフイベントとキャリアを両立できる安心感につながり、人材定着や生産性向上といったメリットをもたらします。
具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- プレコンに関する知識を提供するセミナーの実施
- 専門家による相談窓口の設置
- 不妊治療と仕事の両立を支援する休暇制度や柔軟な勤務体系の導入
あいちフィナンシャルグループでは、新入行員向けにプレコンに関する研修を実施し、高い満足度を得ています。 このように、企業文化としてプレコンへの理解を深める動きは、今後さらに重要になるでしょう。
5. まとめ:プレコンセプションケアは、より良い人生を送るための投資
プレコンセプションケアは、将来子どもを持つことを考えている人だけでなく、 すべての若い世代が自分自身の健康とライフプランについて考えるための重要なツールです。健診(プレコンチェック)は、その第一歩として、自分の身体の「現在地」を正確に知る絶好の機会を提供してくれます。
健診結果を基に生活習慣を見直し、必要であれば専門家の助けを借りながら、健康的な身体づくりに取り組むこと。そして、自治体や企業のサポートを賢く活用すること。これら一つひとつの行動が、あなた自身の未来、そして未来の家族の健康という、かけがえのない財産につながります。
この記事が、あなたがプレコンセプションケアへの理解を深め、具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
参考資料
ドクターコメント
河村寿宏先生より
男女ともに、性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、将来のライフプランも考えながら、健康管理を行うことはとても大切です。 健康な生活を送るための生活習慣としては、適正体重を守る、栄養バランスを整える、適度に運動する、禁煙する・受動喫煙を避ける、アルコールは控えめにする、ストレスをため込まない、などが基本的なものです。 妊娠に関しては、上記の生活習慣を実践するとともに、適切な検査を受けることで、将来に備えることが出来ます。 まずは、プレコンチェックを受け、自分の身体を知ることから始めてみることをお勧めします。
河村寿宏先生プロフィール
田園都市レディースクリニック理事長であり、あざみ野本院の院長を務める河村寿宏先生は、日本の生殖医療をけん引するオピニオンリーダーです。
東京医科歯科大学医学部を卒業後、同附属病院や都立大塚病院での研鑽に加え、デンマーク・コペンハーゲン大学病院への留学で専門性を深められました。帰国後は東京医科歯科大学附属病院産婦人科病棟医長、玉川病院産婦人科医長として不妊専門外来を担当し、2000年に当クリニックを開院されています。
生殖医療専門医・指導医として豊富な経験をもち、国内外の学会でも理事として活躍。
高度生殖医療の分野で多くの患者さんに寄り添いながら、医療の質と温かさを両立させる姿勢が、多くの信頼を集めています。
関連サイト
田園都市レディースクリニック